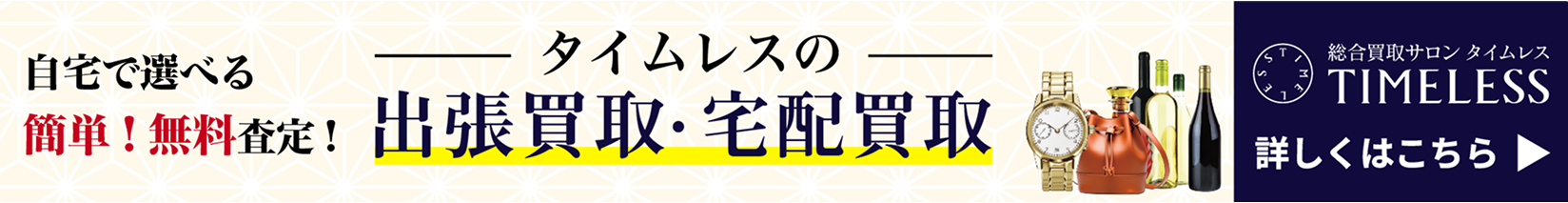正絹を使った着物の買取相場とは?高価買取になる特徴や種類について解説

正絹とは100%の絹糸で織られた生地を指し、生産量に限りがある希少性から高級素材として知られています。
この正絹を用いた着物は、美しい光沢と滑らかな肌触りが特徴で、中古市場でも人気です。
そこで今回は、正絹を使った着物の買取相場について、高価買取の特徴や種類、お手入れのポイントとともに解説します。
Contents

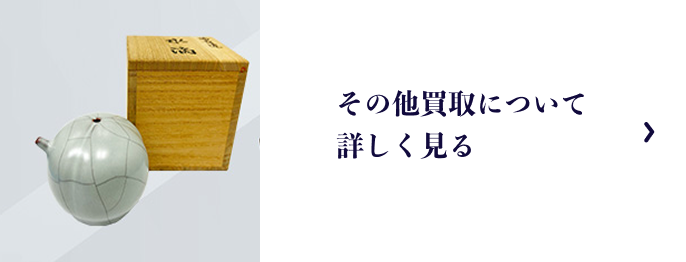
1. 中古着物の需要は増加傾向?近年の動向について
着物全体の市場規模は年々減少傾向にあります。
単純に着物を着用する機会が減っている点や、近年の新型コロナウイルス感染症拡大や経済不況によってライフラインの充足が優先されている点が主な理由です。
その中で、正絹を使った高級着物を新しく購入する方は、以前よりもさらに少なくなりました
ただし、減少傾向とはいえ冠婚葬祭や季節のイベントで振袖などの晴れ着を着用する方は一定数いらっしゃいます。
その中で、近年需要が高まっているのが中古の高級着物です。
中古の高級着物の需要が高くなってきた理由としては、主に以下の点があげられます。
- 素材や作家によってヴィンテージ品になっている
- 海外での需要が増えている
- レンタルサービスに活用される
ここでは、中古の高級着物の需要が高くなった理由について深掘りしていきましょう。
1-1. 素材や作家によってヴィンテージ品になっている
希少性のある素材や有名作家が手がけた着物は、時代を経るにつれてヴィンテージ品扱いされており、コレクターからの需要が高いです。
特に正絹については、株式会社和想 代表取締役社長 池田訓之の著書『君よ知るや着物の国』で「昔の正絹のほうが質がいい」と記されています。
このことからも、正絹を使った中古着物の価値、質を求める方からの需要が判断できるはずです。
また、現代において緻密かつ精巧な技術を持った着物職人は減少傾向であり、著名な作家のデザインが神格化されつつあります。
京友禅・加賀友禅でおなじみの羽田登喜男の作品も、買取価格が10万円以上になるケースも珍しくありません。
1-2. 海外での需要が増えている
海外の着物需要が増加しており、販売ルートが拡大している点も中古着物市場に大きく影響しています。
海外における着物への注目の高まりは、フランスの国立ギメ東洋美術館で「Kimono, Au bonheur des dames」やイギリスのヴィクトリア&アルバート博物館の「Kimono:Kyoto to Catwalk」など、著名な美術館・博物館で着物の特集が開催されていることからもわかります。
着物には、四季折々の模様と色合いが表現され、芸術性の高さや日本の伝統を感じられるとして海外から評価されています。
また、アニメの浸透によって日本に関心を抱く方も増えており、その影響で着物を認知している方も少なくないでしょう。
こうした着物の認知がグローバルに拡がり、実際に着用してみたい方や品質を見極めてコレクションをしたい方が国内の垣根を超えて増えつつあるのです。
1-3. レンタルサービスに活用される
中古着物は購入だけでなく、レンタルサービスやサブスクリプションサービスで活用されます。
国内での着物利用シーンは季節の行事やイベント時といったように限られており、それ以外ではめったに用いられません。
利用機会が少ないと着物のメンテナンスが手間になるので、必要時にレンタルサービスを選ぶ傾向があるのです。
めったに着用する機会がなければ、少し奮発して美しく光沢のある高級着物を着たくなるもの。
上記の理由から、正絹を使った高級着物は、レンタルサービス提供側への販路もあると考えられます。
2. 正絹を使った着物の種類
正絹を使う着物には、どのような種類があるのかご存じでしょうか。
ここでは、正絹が使用される9種類の着物の特徴について簡単にご説明します。
2-1. 打掛(うちかけ)
打掛は結婚式に花嫁が着用する、着物の中では最も格式高い婚礼衣装です。
小袖や振袖の上から打ち掛けて(そっと羽織る)着用するのが名前の由来で、白無垢・色打掛の2種類あります。
白無垢は名前の通り白一色で織られた純白の打掛で、結婚式のみで使用される着物です。
一方、色打掛は鮮やかかつ豪華な柄が特徴的で、結婚式以外にも披露宴や神前式でも用いられることがあります。
2-2. 黒留袖(くろとめそで)
黒留袖は、既婚女性が着用する礼装で、黒地に両胸、両後袖、背中に五つ紋が入っており、重ね着のような比翼仕立てが特徴です。
一昔前までは結婚式や結納式で新郎新婦の母親や仲人夫人などが着用していましたが、現在では訪問着や他の着物で簡略化されている傾向にあります。
黒留袖に関しては、通年で着用できるよう季節を感じさせない柄が施されているケースが多いです。
2-3. 色留袖(いろとめそで)
色留袖は黒地以外の生地を使用した留袖で、既婚・未婚問わず着用できる礼装です。
色や柄の種類が豊富にあり、フォーマル用として汎用性が高いため、結婚式や成人式の晴れ着などで利用されます。
デザイン性の幅から、年齢層に関係なく多くの方に好まれているのが色留袖の特徴です。
2-4. 訪問着(ほうもんぎ)
訪問着は、既婚・未婚に関係なく着用でき、留袖よりもカジュアルなシーンで用いられる準礼装です。
留袖は絵羽模様が裾にのみ入っていますが、訪問着は上半身にも入っているため、一目で両者の違いが判断できます。
また、訪問着は絵柄が着物全体にひと繋ぎで続いている点も特徴です。
2-5. 振袖(ふりそで)
振袖は、袖丈を長く仕立てた和服で、主に20代〜30代を中心とした若年層の第一礼装として知れ渡っています。
袖丈の長さによって大振袖・中振袖・小振袖と分かれており、大きいほど格式が高いとされています。
元々日常着として用いられた小袖が、江戸時代前期から後期にかけて袖丈が長く派生していったのが振袖の起源です。
振袖の豪華な柄は、成人式や卒業式、パーティーなどお祝いの場に相応しいデザインといえるでしょう。
2-6. 付け下げ(つけさげ)
付け下げは絵羽模様がない、あるいは控えめに施されているのが特徴の着物で、格式の高さは訪問着に準じているのが特徴です。
派手すぎない落ち着いた柄が人気で、価格帯も着物の中では中間に位置するため、市場でも一定の需要があります。
2-7. 色無地(いろむじ)
色無地は、黒以外の一色で生地を染めた柄のない着物です。
地紋がないタイプはさらに以下の4種類の素材にわけられます。
- 縮緬(ちりめん)
- 一越(ひとこし)
- 二越(ふたこし)
- 三越(みこし)
家紋を入れると、訪問着などの格式高い礼装として着用もできる汎用性の高さも色無地の魅力です。
2-8. 小紋(こもん)
小紋は生地全体に同じ柄・模様が施されているのが特徴の着物です。
現在において模様の大小は区別なく小紋と呼ばれ、主に普段着や食事会、同窓会などカジュアルな行事で用いられています。
小紋の種類については江戸小紋・京小紋・加賀小紋の3種類が有名で、それぞれの地方で習熟された技巧が体現されています。
2-9. 紬(つむぎ)
紬は糸の状態から染色をして紡がれた着物で、素朴で落ち着いた風合いが特徴です。
「先染めの着物」として知られ、色落ちしにくく丈夫で、普段着やおしゃれ着として用いられます。
紬は産地が多く、鹿児島県の大島紬や茨城県の結城紬、石川県の牛首紬が日本三大紬として有名です。
3. 著名な作家
着物の買取相場を知る上で、著名な作家は価値を決める重要な要素の1つです。
ここでは、着物に関する著名作家を簡単にご紹介します。
3-1. 久保田一竹(くぼたいっちく)
久保田一竹は、室町時代から安土桃山時代にかけて流行した絞り染めの技法「辻が花」を独自解釈で復刻させた染色工芸家です。
後に「一竹辻が花」と呼ばれるその技法は、2代目である悟嗣氏に受け継がれ、なおも伝統を守り続けています。
3-2. 木村雨山(きむらうざん)
木村雨山は、絹織物が盛んな石川県金沢市で生まれ、1955年に重要無形文化財技術保持者として人間国宝に認定された著名作家です。
その生涯を費やしたほど加賀友禅に魅了され、柄や模様に日本画で学んだ技法と自然美を取り入れることで、重厚感のあるデザインを体現しています。
3-3. 上野為二(うえの ためじ)
上野為二は、友禅染を家業にしている父のもとに生まれ、京友禅と加賀友禅を融合させた独自の染色技術で1955年に人間国宝に認定された作家です。
京友禅の華やかさがありながら、加賀友禅の落ち着きのあるデザインを調和させ、気品と美しさのある友禅を残しています。
3-4. 羽田登喜男(はた ときお)
羽田登喜男は、14歳のころに加賀友禅、20歳には京友禅を学び、「羽田友禅」と呼ばれる独自技法によって人間国宝に認められた有名作家の1人です。
特に夫婦円満の意味でもある「おしどり」の模様を取り入れたのが人気で、国内外から高い評価を受けています。
3-5. 由水十久(ゆうすい とく)
由水十久は生涯にわたって加賀友禅を磨き続けた有名作家の1人です。
童子をモチーフにした作品で広く知られ、1977年には伝統工芸士、1978年には石川県の指定無形文化財加賀友禅技術保持者に認定されています。
3-6. 芹沢銈介(せりざわ けいすけ)
芹沢銈介は、静岡県出身の重要無形文化財技術保持者、つまり人間国宝に認定された伝統染色家です。
独自の染色技術を用いた「いろは柄」は、色とりどりのひらがなが着物全体に装飾されています。
3-7. 志村ふくみ(しむら ふくみ)
志村ふくみは31歳のときに織物と出会い、以降は紬織によって1990年に人間国宝と認定された染色作家です。
特定の師を作らず、自らで研鑽を積んでいくうちに、多彩で生命力あふれる色合いを習得し、独自の作風が今日の世界的評価を獲得するにいたりました。
3-8. 森口華弘(もりぐち かこう)
友禅染の第一人者である森口華弘も、覚えておくべき著名作家です。友禅染めの豪華な色あいをあえて抑え、色の濃淡によって気品のあるデザインを誕生させています。
2008年には重要無形文化財保持者として認められ、現在の友禅の始祖として今もなお語り継がれています。
3-9. 小宮 康正(こみや やすまさ)
小宮康正は伝統と先進的な技術の融合によって、伝統的染色技法を牽引してきた作家です。
江戸小紋で人間国宝に認定された小宮康助のもとで修行し、2018年に重要無形文化財「江戸小紋」の保持者に認定されています。
3-10. 北村武資(きたむら たけし)
北村武資は、2000年に重要無形文化財保持者に認定された作家です。
飽くなき探究心によって生まれる革新的な織の技術は、常に驚きと感動を与えるほど並外れたデザインとなっています。
4. 高価買取になる正絹を使った着物の特徴
ここでは、正絹を使った着物の中でも、高価買取になる着物の特徴についてご紹介します。
4-1. 高度な技術・製法で作られた着物
正絹はしなやかで光沢があり、糸の密度や染色の美しさが仕上がりを大きく左右します。
そのため、友禅染めや絞り、織りの技法など高度な職人技術と製法で作られた正絹の着物は特に評価が高く、高価買取される可能性が高いです。
例えば、京友禅や加賀友禅といった精緻な染め技法を用いた着物は、正絹の光沢を最大限に活かし、他の素材では再現できない美しさを生み出します。
中古着物とはいえ、美術的価値と工芸品としての価値が高いからこそ、高価で取引される素質があると判断できるでしょう。
4-2. 有名作家・人間国宝が手がけた着物
有名作家や人間国宝が手がけた着物はまさに高級品。そもそもが高価なので買取時にも高くなりやすいです。
作家独自の染色法や織り技術は、正絹の上質な素材だからこそより映え、他の素材よりも付加価値がつきます。
著名作家である木村雨山や羽田登喜男らが手がけた着物は、10万円以上の価値で取引されるケースも珍しくありません
正絹の着物は作家の技術力・芸術性が表れやすいからこそ、買取市場でも人気があります。
4-3. 証紙・落款がある着物
着物の産地や作家を証明する証紙や落款があるかどうかも、高価買取に影響する要素です。
証紙や落款はいわば名刺のような役割で、その着物がどこで誰が作ったものかを保証します。
熟練の鑑定士が正絹の質感や光沢を見極めるのは当然ですが、証紙や落款があることで、より価値を引き出せる要因となります。
4-4. 保存状態が良い着物
正絹はデリケートな天然素材であるため、保存状態によっても買取価格は変動します。
シミやカビ、虫食いがあると、たとえ名品だとしても評価は下がってしまうでしょう。
一方で、色焼けや臭い移り、汚れが少なく新品に近い保存状態なら、高額査定の対象です。
着物は美しく着てこそなので、普段から正しい保存をしておくことが価値を下げない方法だといえます。
5. 正絹を使った着物のお手入れのポイント
正絹を使った着物をきれいな状態で保存するには、使用時および適切な間隔でお手入れをすべきです。
では、どのようなお手入れをすればいいのか、そのポイントについて解説します。
5-1. 着用後はハンガーにかけて湿気を逃す
正絹は湿気に弱く、放置しておくとカビや臭いの原因になります。
着用後は桐製あるいは着物専用のハンガーにかけ、風通しのよい場所で半日から一日ほど陰干しをしましょう。
直射日光に当ててしまうと色焼けを起こしてしまい、正絹の着物本来の美しさが底なってしまう可能性があるので注意してください。
5-2. シミ・汚れをチェックする
正絹の着物を陰干ししたあとは、シミ・汚れがないかチェックしてください。
シミ・汚れは早めのほうが取り除きやすく、手間も少ないです。
チェックする際は、袖口や裾などの汚れやすい部位を重点的に確認しましょう。
汚れを見つけたら小さい範囲でも放置せず、生地を傷めないように専門のクリーニング業者に依頼するのが適切です。
5-3. たとう紙に包んで収納する
正絹の着物のシミ・汚れチェックが済んだら、たとう紙に包んで収納および保管しておきます。
たとう紙は着物に湿気をこもりにくくしてくれますが、もし手元にないなら乾燥剤や除湿シートで代用も可能です。
5-4. 年に数回の虫干しを行う
収納後の湿気やカビ、虫害から着物を守るため、年に数回は虫干しをおすすめします。
虫干しは、風通しのよい場所で陰干しすることを指しているため、何ら難しい方法ではありません。
湿気を逃すことが目的なので、時期としては以下のタイミングが最適です。
- 7月下旬〜8月上旬:梅雨で湿気が増えているため
- 9月下旬〜10月中旬:夏についた虫を取り除くため
- 1月下旬〜2月下旬:湿気・虫を取り除くため
虫干しを行う際は、天気がよい日の午前中から午後のうち3〜4時間程度行いましょう。
6. 正絹を使った着物の買取相場
正絹を使った着物は一般的な着物よりも市場に出ておらず、買取価格が把握しづらいのが現状です。
その中でも、おおよその買取相場がわかるのは、打掛・黒留袖・色留袖の3種類です。
| 種類 | 相場 |
| 打掛 | 5,000〜150,000円 |
| 黒留袖 | 3,000~200,000円 |
| 色留袖 | 3,000~200,000円 |
※価格はお品物の保存状態・売却タイミング・柄・作者等によって変動します。上記は正絹の美品を想定した価格帯になります。
7. まとめ
美しい色合いと肌触りのよさが魅力の正絹は、着物の買取市場でも高値がつくほどの希少性のある素材です。
その希少性と美術的価値、工芸品としての価値から、中古着物でも高値で取引される傾向があります。
もし正絹を使った着物の処分に困っている方がいらっしゃいましたら、一度買取の見積もりを検討してみてはいかがでしょうか。


ご自宅に眠っている正絹のお着物はございませんか?
大手百貨店やショッピングモールに店舗を展開し、信頼と実績の買取でご好評をいただいている総合買取サロン タイムレスにお任せください。
📌お着物の売却を検討している方へ
箪笥の中で眠っているお着物はありませんか?思い出の品であったり大事な方から受け継いだものであったり、処分しづらいお着物は、次の方へバトンを渡してみてはいかがでしょうか。状態や希少性によって査定額は大きく変わるため、売却をご検討の際はぜひ着物に詳しい専門業者に相談してみてください。
タイムレスではプロの査定員が丁寧に鑑定し、ご納得いただける買取をめざしています。無理な買取、強引な営業の心配は無用です。ぜひお気軽にご相談ください。
「価値があるのかどうか分からない」「こんな物売れるの?」
そんなお品物でもぜひお持ちください。
その他:古銭・ブランド食器・楽器・骨とう品・カメラなど
※買取対象品目は店舗・催事ごとに異なります
※また、未成年者からの買取はできません。酒類の買取に関しては20歳以上のお客様のみ対象となります。各店舗・催事ページをご確認いただくか直接お問い合わせください
選べる買取方法
タイムレスでは、お客様のご都合に合わせた様々な査定・買取方法をお選びいただけます。